牛のケトーシスの定義
乳牛の職業病とも言える疾患で、「獣医内科学 大動物編」によると「生体内にケトン体が異常に蓄積し、臨床症状を呈した病態」と定義されている。ケトン体とは、牛の体内で生成されるアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸(=3-OHBA)、アセトン等の総称である。
牛のケトーシスの分類
「牛の臨床 第三版」では、ケトーシスは以下のように分類されている。
上記の様に、臨床症状の有無の2分類と、ケトーシスの原因による3分類がなされている。
牛のケトーシスの原因
Ⅰ型ケトーシスは、分娩後のエネルギー不足が原因で起こる。分娩後3〜6周目の泌乳ピークに起こりやすい。慢性的な低血糖と低インスリンを主症状とする。人のⅠ型糖尿病に類似するので、Ⅰ型ケトーシスと呼ばれる。プロピレングリコールの給与や点滴治療に反応しやすく、予後は良い。
Ⅱ型ケトーシスは、前の記事でも挙げたが、乾乳期に食欲が低下し、低エネルギー状態となることが引き金となる。低エネルギー状態により体脂肪が動員され、脂肪肝となることが原因で起こる。(参照https://www.damevet-4-6.com/乳牛と脂肪肝とケトーシス/)。分娩後1〜2週目に起こりやすい。肝機能の低下により、糖新生が進まなかったり、インスリンへの感受性が低下する。第四胃変位や感染症を併発しやすいので、予後はあまり良くない。人のⅡ型糖尿病に類似するので、Ⅱ型ケトーシスと呼ばれる。乾乳期に太っている牛は、低エネルギー状態になり易く、Ⅱ型ケトーシスになり易いので注意が必要である。
食餌性ケトーシスは、変敗して酪酸を多く含んだサイレージの給与が原因で起こる。サイレージ調整が上手くいかないと乳酸発酵が進まず、クロストリジウム属菌が増殖し、ブドウ糖や乳酸から酪酸を大量に生成してしまう。酪酸を大量に摂取した牛の体内では、ルーメンで代謝しきれなかった酪酸が、血中でβヒドロキシ酪酸に変化する。治療と飼料の変更により、予後は良い。
牛のケトーシスの症状
臨床型ケトーシスの症状
①活力と食欲の低下(配合飼料よりも粗飼料好む)
②泌乳量低下
③神経症状
④体表、呼気などのアセトン臭
潜在性ケトーシス
①目に見える臨床症状はない
②泌乳量の低下(1〜4ℓ/日減)
③繁殖成績の低下
④感染症に罹患し易くなる
食餌性ケトーシス
①食欲低下
②泌乳量低下
③軟便、未消化便
牛のケトーシスの診断方法
○乳汁中ケトン体測定用紙(サンケトペーパー 東洋濾紙株式会社)
乳汁中のβ-ヒドロキシ酪酸を色で判定する濾紙であり、簡易的な検査としては手軽で現場で使用し易い。濾紙の判定基準は以下の通り。1
乳汁中のβ-ヒドロキシ酪酸濃度 判定ランク
0〜50μmol/L 正 常(-)
100μmol/L 擬陽性(±)
200μmol/L 陽 性(+)
500〜1000μmol/L 強陽性(++)
これに対して、牛の乳汁中のβ-ヒドロキシ酪酸の濃度は、健常泌乳初期牛で100〜560μmol/L、ケトーシス牛で340〜1200μmol/Lと言われている。2
特異度(病気でない牛が陰性と判定される割合)が高く、感度(病気の牛が陽性と判定される割合)は低いと言われている。
○乳検データ
乳検データの個体情報から、乳中β-ヒドロキシ酪酸を見ることができる。乳検DLの上の「公開情報」タブから牛群の個体情報を表示すると、乳検当日の牛のβ-ヒドロキシ酪酸がわかる。乳検当日のデータなので、リアルタイムな情報ではないが、ケトーシスが疑われる牛がピックアップできる。
0.13mM/Lが基準値で、この値を超えるとケトーシスが疑われる。特に分娩後、60日以内の牛については確認しておくべき数値である。
○血中β-ヒドロキシ酪酸の測定
血中のβ-ヒドロキシ酪酸が1.2mMでケトーシス陽性であり、3.0mM以上で臨床症状が出ていることが多い。3
牛のケトーシスの治療方法
○糖源物質の経口投与
①プロピレングリコールの投与
・体内でプロピオン酸に代謝される。
・300mLを3〜5日間経口投与。
②グリセリンの投与
・体内でグルコースとなり、エネルギーの補給になる。
・安価である。
・300mLを3〜5日間経口投与。
牛のケトーシスの予防方法
Ⅰ型ケトーシスの予防としては、移行期の餌のエネルギー不足をなくすこと、餌槽スペース(76㎝/頭以上)と水場が十分に確保されていること、スリーストールなら牛床がしっかりと確保されていることが重要となる。
Ⅱ型ケトーシスの予防は、乾乳後期にエネルギー不足になりにくいような飼養管理が重要である。特に乾乳牛への適切な飼料設計、乾物摂取量が低下しない飼養管理が問われている。乾乳までにBCSを適正にしておくことや分娩予定日2週間以内に移動しないことは、乾物摂取量の低下を抑える重要な管理である。移行期にルーメンバイパスコリン(水溶性ビタミン様物質)やメチオニン(アミノ酸)の添加を行うことは、肝臓脂肪化軽減に有効である。3
- 動物用医薬品データベース、サンケトペーパー、https://www.vm.nval.go.jp/public/detail/4831 ↩︎
- 家畜共済の治療指針 Ⅰ、p84 ↩︎
- 産業動物臨床医学雑誌、及川伸、4巻3号:118-124、2013 ↩︎
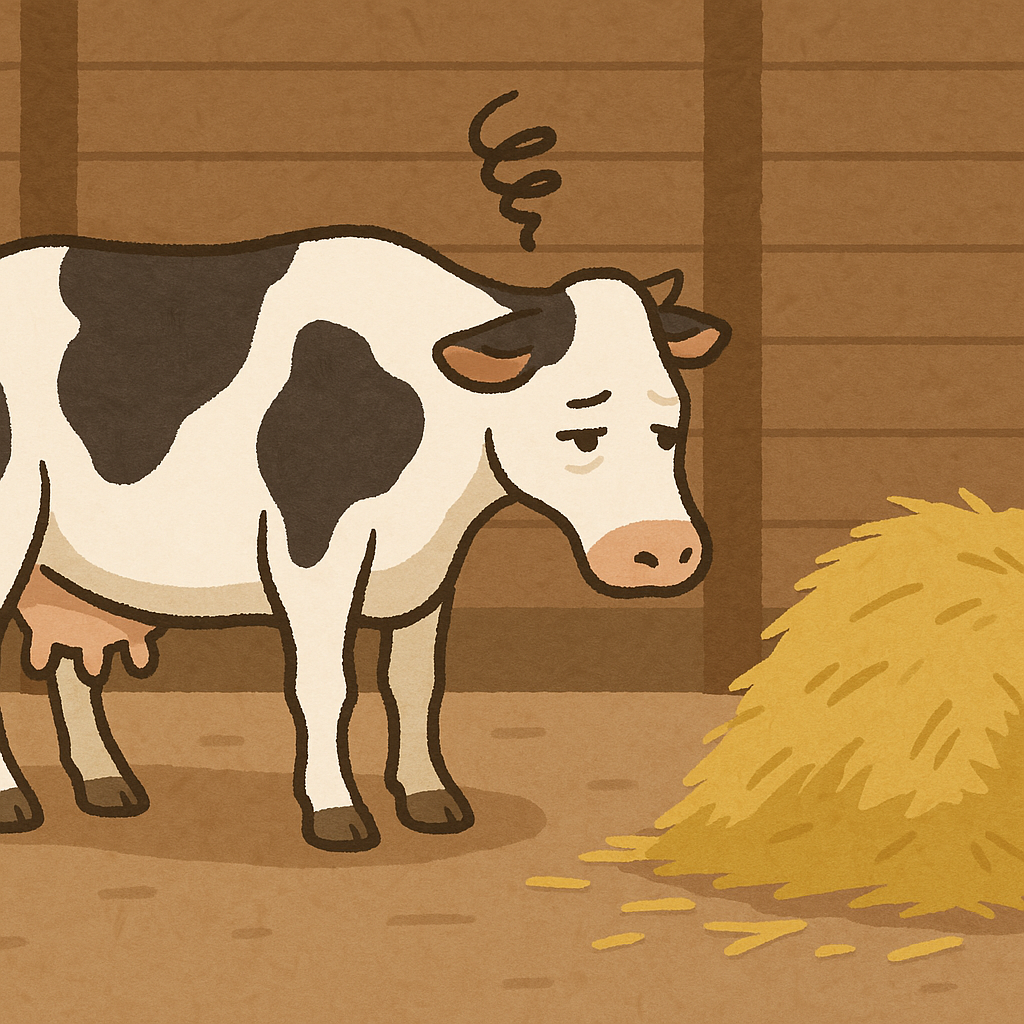

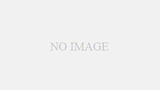
コメント