分娩直前から分娩後2日程度に発症し易い、代謝性疾患で、乳牛の代表的な病気の一つで、農家さんから、「腰抜け」と呼ばれている疾患です。
傾向としては、泌乳能力が高い乳牛ほど罹患しやすい傾向があります。
1) 定義
分娩する乳牛では生理的に血中のカルシウム濃度が低下し易く、著しい症例では意識低下、骨格筋の弛緩麻痺を主徴とする無熱性の起立不能症を発症し、乳熱と呼ばれている。1
2) 原因
分娩後の泌乳開始に伴い、急激にカルシウムが乳汁へと流出することが根本的な原因といわれている。また、分娩前後の副腎皮質ホルモンやエストロジェンの影響により、腸管の蠕動運動が抑制され、骨代謝が抑制されており、腸管や骨からのカルシウム吸収では、血中のカルシウム濃度の急激な低下にすぐに対応できないといわれている。そして、分娩時に上皮小体ホルモン(PTH)の分泌が抑制されることも、本症例の発症に関与している。詳しくはDCADとPTHの関係を参照。
3産目以降の牛に発症しやすいのは、加齢に伴い泌乳量が増加することで、血中カルシウム濃度がさらに急激に低下するためといわれている。
3) 症状
軽度の乳熱(血中Ca濃度:6.5mg/dL〜)では、食欲不振、歯ぎしり、筋肉の振戦、後肢のふらつきなどの症状がみられる。
中等度の症例(血中Ca濃度:3.5〜6.5mg/dL)では、起立不能状態、食欲の低下、心拍数の増加、子宮収縮の低下などの症状がみられる。
重度の症例(血中Ca濃度:3.5mg/dL以下)では、投首投足、昏睡状態になる。体温は一般的には低下し、38.0度を下回る症例が多いが、39.0度を超える症例も時折みられる。
乳熱では、対光反射の遅延や不全(眼に強い光を当てた時の瞳孔の収縮遅延、収縮不全)がみられることもあり、大腸菌性乳房炎によるショック状態による起立不能か、乳熱による起立不能かを見極める際に、参考にすることができる。
4) 治療
○カルシウム製剤の注射による補給
静脈注射: ボログルコン酸カルシウムなどのカルシウム製剤を静脈注射する。これは迅速に血液中のカルシウム濃度を上昇させるため、最も効果的な方法。
皮下注射: 静脈内注射が難しい場合、カルシウムを皮下に注射することもあるが、効果は静脈注射に比べて血中カルシウム濃度の上昇が遅い。効果が長く続くのが利点で、約1日間続く。
経口補給:カルシウムペーストを経口で投与する方法。主に予防目的で使用されるが、軽度の症状に対しても有効。
○その他の補助療法
低カルシウム血症だけでなく、低マグネシウム血症や低リン血症を併発していることもあり、同時に補給することも有効。特にマグネシウムの著しい低下は、振戦(筋肉の震え)や重度の歯軋り、流涎などの激しい症状を伴うこともある。スラリーを撒いて牧草を作っている農家さんで発生し易いため、過去に低マグネシウム血症が発生しているかどうかを聞き取りすることは、非常に重要だと感じる。
脱水症状がある場合には、電解質液の静脈輸液が行われることもある。また、低カルシウム血症により、血管の平滑筋が弛緩し、血液循環が悪化しているため、カルシウム製剤の投与とともに血液循環の改善を行うことで、治療効果を高めることができると考えられている。特にカルシウム製剤と高張食塩水の同時投与は、高張食塩水による血液の酸性化により、血中のイオン化カルシウムの割合を高め、乳熱の治療効果を高めると考えられている。
5) 予防
○乾乳期のDCADの管理
低DCAD飼料の給餌:乾乳期には、塩化アンモニウムや硫酸マグネシウムなどの添加剤を用いてDCADを低く保つことが重要。目標とするDCAD値は -50 mEq/kgから -150 mEq/kg。
尿pHのモニタリング:尿pHを定期的に測定し、6.0~7.0の範囲を維持する。これにより、代謝性アシドーシスの状態を確認し、飼料のDCADが適切であることを確認できる。また、乾乳期にアルファルファなどの高カリウム飼料を避け、低カリウムの飼料を選ぶ。
○分娩前後のカルシウムの適切な給与
分娩前(乾乳期)には、飼料中のカルシウムを0.4~0.6%程度に制限する。また、アルファルファ乾草やカルシウムが多いミネラル飼料を避ける。分娩兆候が見られたら、カルシウムを経口投与してやる。
○ビタミンDの補給
ビタミンDはカルシウムの吸収を助けるため、分娩前に適切な量を投与する。
筆者は分娩予定5〜8日前にビタフラルD3-S(共立製薬)を半量5mL投与し、予定日を過ぎた場合にさらに半量の投与を推奨している。
○ストレス管理
分娩前後のストレスはカルシウム代謝に悪影響を与えるため、乾乳牛がリラックスできる環境を整えることが重要。特に概ね10〜12㎡/頭の広さが必要と言われている。
分娩直前(分娩予定日1週間以内)の移動や環境の変化を最小限にすることで、分娩前ストレスを低減する。
6) まとめ
乳熱は迅速な治療が必要な病気であり、発症後の早期対応が牛の回復にとって非常に重要となる。また、他の周産期疾病(産褥熱、ケトーシス、第四胃変位など)の発症に関わりのある疾病なので、周産期で失敗しないためにも避けるべきである。適切な管理と予防策を講じることで、発生率を減少させることができる。
参考文献
- 山岸則夫(2012).乳熱の病態.日本獣医師会雑誌.65巻11号.857-863 ↩︎

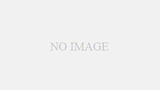
コメント