Contents
定義
産褥熱とは何か
牛の産褥熱(metritis)は、分娩後10日以内に発症する急性の全身性の細菌感染症。主な感染部位は子宮で、起因菌が産道や子宮に侵入し、炎症反応が全身に及ぶことで高熱・食欲廃絶・乳量減少などを引き起こす。早期発見・治療が遅れると敗血症に進行し、死亡や廃用に至ることもある。
発生頻度と経済的損失
- 発生率:国内外のデータでは、平均で乳牛の約20%が分娩後に発症。初産牛や介助分娩では発症率が50%近くに達することもある。
- 経済的損失:
- 米国の試算では1頭あたり240〜884ドル(約3〜12万円)の損失
- 日本の事例では100頭群で繁殖損失だけで約50万円、乳量減少・治療費を含めるとさらに増加
- 損失要因は、乳量減少(発症後30日以内に日量3〜6kg減)、繁殖成績低下(受胎遅延・不妊)、淘汰率増加など
原因と発生機序
分娩後の子宮感染(細菌感染の主要経路)
- 分娩直後は子宮頸管が開き、外界からの細菌侵入が容易
- 分娩介助時の器具・手指の汚染も感染リスク
- 胎盤停滞による、後産の腐敗
起因菌
- 好気性菌:大腸菌、連鎖球菌、ブドウ球菌
- 嫌気性菌:Fusobacterium necrophorum、Bacteroides属など
- 混合感染が多く、嫌気性菌優位だと悪臭が強く重症化しやすい
分娩時の外傷・難産との関係
- 子宮頸管裂傷や産道外傷は菌の侵入門戸となる
- 難産・胎盤停滞が発症リスクを大幅に高める
免疫低下や代謝疾患との関連
- 低カルシウム血症(乳熱)やケトーシスは好中球機能低下を招き感染防御力低下
- 高産次牛や過肥牛は発症リスクが高い
臨床症状
- 体温:39.5℃以上(重症例では41℃超)
- 消化器症状:食欲低下、反芻停止
- 泌乳:乳量の急減
- 子宮排出物:灰白色〜褐色で悪臭
- 全身状態:沈鬱、脱水、頻脈
診断
臨床所見による診断
- 高熱+悪臭排出物+全身状態悪化が3徴候
- 直腸検査で子宮腔拡張、内容物貯留確認
子宮内容物の観察・スメア検査
- スメア染色で好中球多数、細菌の形態確認
- 後産の有無の確認
血液検査
- 産褥熱でみられる主な血液検査異常
① 白血球数(WBC)と分画
急性炎症期(発症初期)
白血球増多(WBC > 12,000/μL)
好中球の核左方移動
重症敗血症や慢性化
白血球減少(WBC < 4,000/μL)
骨髄抑制または末梢消費優位
重症例では好中球の著減が予後不良サイン
② 急性期タンパク(APPs)
フィブリノーゲン(Fbg)
健康牛(200〜400 mg/dL)に対して、産褥熱牛では500〜1,000 mg/dL以上に上昇
産褥熱ではFbgが700 mg/dLを超えることが多い
血清アミロイドA(SAA)
急性炎症に鋭敏に反応(健康牛で <10 μg/mL → 発症時は数百 μg/mLまで上昇)
特に発症早期の感度が高い
ハプトグロビン(Hp)
健康牛ではほぼ検出されない(<0.1 g/L)
発症時に著明に上昇(1〜3 g/L)
③ 血液化学検査
血糖(Glucose)
健康時:50〜60 mg/dL
感染・炎症時:食欲低下+エネルギー消費増加で低下(<40 mg/dL)
総蛋白(TP)・アルブミン(Alb)
TPは脱水で一時的に上昇するが、慢性炎症では低下
Albは炎症時のネガティブ急性期タンパクとして低下
BUN(尿素窒素)
食欲低下や蛋白分解で上昇傾向
電解質異常
Na:下痢や膿排出による喪失で低下
K:食欲不振で低下(<3.5 mEq/L)
Cl:嘔吐はないが第四胃変位併発時に低下
Ca(カルシウム)
低Ca血症が好中球の機能を抑制し悪化要因となる
発症牛の多くで軽度〜中等度の低下(<8.5 mg/dL)
④ 血液ガス分析
敗血症性ショックや重度脱水例では代謝性アシドーシス(HCO₃⁻低下、BEの低下)
重症敗血症では乳酸上昇(>2 mmol/L)
治療法
全身療法(抗菌薬)
- ペニシリンG+ストレプトマイシン
- 第3世代セフェム系(セフチオフルなど)
- アンピシリン
- 投与期間:解熱後3〜5日継続
子宮局所療法
- 適応:子宮頸管が開いており、排膿可能な症例
- 子宮内薬剤注入:β-ラクタム系を使用する。悪露が入っているところに抗生物質を入れても、効果は懐疑的であり、耐性菌が出る可能性があるのであまり推奨されない。
- 子宮洗浄:漏斗と太めのチューブを使用する。子宮内にチューブを挿入し、漏斗を用いて水道水を子宮内に注入し、溢れそうになった所で、サイフォンの原理で悪露と水道水を排出する作業を灌流液が透き通ってくるまで複数回実施する。残った後産の破片がチューブの先に詰まることがある。
全身管理
- 補液療法:酢酸リンゲル、高張食塩水、ブドウ糖の投与。
- 解熱・消炎剤:フルニキシンの投与。ステロイド剤は胎盤の落ちと悪露の排泄が悪くなるので、推奨されない。
- 栄養補給:プロピレングリコール、ビタミンB群の投与
予後と繁殖への影響
- 発症牛は受胎率低下(表1)
- 再発や難治化で廃用リスク上昇
| 項目 | 健康牛 | 産褥熱罹患牛 |
| 受胎までの日数 | 85〜95日 | 110〜140日 |
| 初回人工授精受胎率 | 40〜50% | 20〜30% |
| 廃用率(産褥熱関連) | 5〜7% | 15〜25% |
予防
産褥熱の原因となる後産停滞のリスクが上がる要因
①分娩・繁殖管理に関する要因:
難産
長時間の分娩による子宮疲労・収縮力低下
胎児過大や胎位異常
介助分娩や帝王切開による外傷・炎症
早産・流産
胎盤成熟不全による剥離遅延
双子分娩
子宮伸展過多による収縮低下
②栄養・代謝要因
カルシウム不足(低カルシウム血症)
子宮筋収縮力低下
エネルギー不足(負のエネルギーバランス)
ケトーシス・脂肪肝による免疫低下
ビタミンE・セレン欠乏
抗酸化機能低下による胎盤剥離障害
タンパク質・ミネラルのアンバランス
免疫機能の低下や胎盤の退行不全
③感染、炎症要因
分娩時の子宮内感染(大腸菌、連鎖球菌など)
炎症により胎膜剥離が阻害
胎児死産や腐敗胎児
子宮環境悪化と剥離不全
分娩環境の不衛生
細菌感染リスクの増加
以上の要因から、分娩前の栄養管理(Ca・E・Se)、分娩環境の衛生、乾乳期と分娩後の飼養管理、難産予防が特に重要となる。また、分娩後2〜4時間以内のオキシトシン投与(30単位、3mL)も有効と言われている。1 超音波検査で、双子が妊娠しているとわかった個体は、予定日が早まる可能性が高いので、分娩予定日の2週間程前から濃い目の餌を与えて備えておくことも重要である。
分娩後5日経っても後産が落ちない場合は、獣医師に胎盤除去を依頼し治療してもらうことも重要である。
まとめ
- 産褥熱は分娩後の緊急感染症
- 産褥熱の早期発見・早期治療が損失軽減の鍵
- 獣医師と酪農家が連携し、発症リスクを最小化する管理体制が重要
- A Mollo. Anim Reprod Sci. 1997 Jul;48(1):47-51. ↩︎


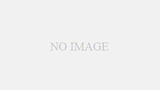
コメント